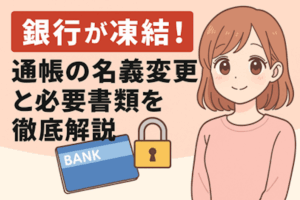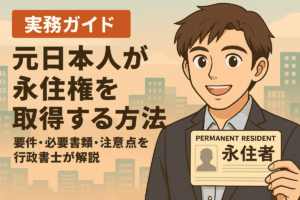【見落とし注意】登録支援機関の更新でやってはいけない3つの落とし穴|専門家が徹底解説
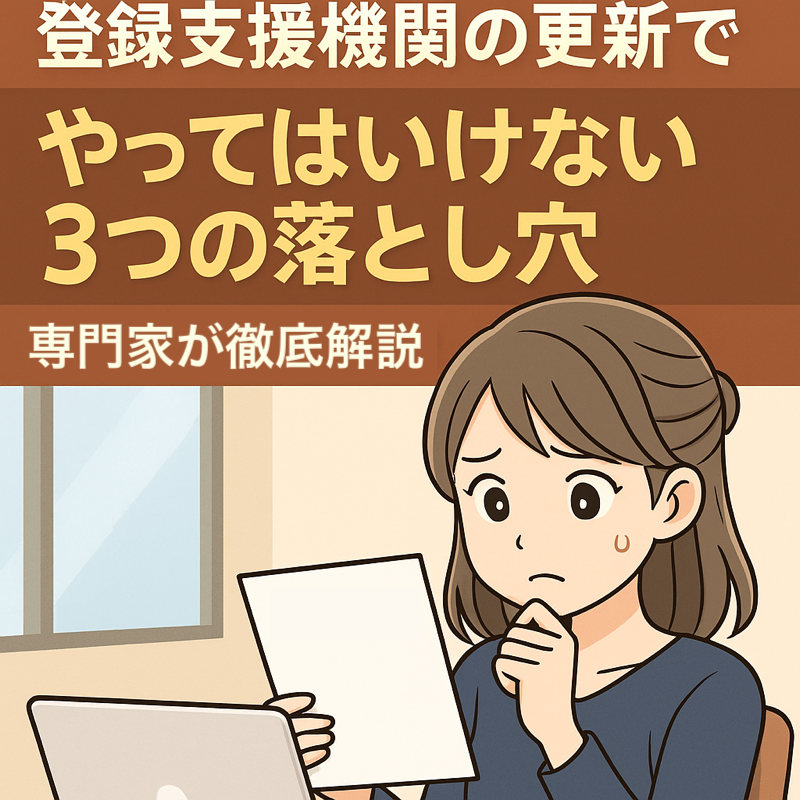
【見落とし注意】登録支援機関の更新でやってはいけない3つの落とし穴|専門家が徹底解説
登録支援機関の有効期限が迫っているけれど、「活動していなかったから大丈夫だろう」と思っていませんか?それ、非常に危険です。2023年度における登録支援機関の更新却下率は全国で約6.2%(出入国在留管理庁発表)というデータもあり、見過ごしがちな点で不利益を被る事例が散見されます。
本記事では、登録支援機関の更新時にありがちな見落としや専門家しか知らない実務の注意点について、実際の統計や現場での事例も交えて、詳しく解説します。
東松山、滑川町、坂戸市、川越市、熊谷市などで登録支援機関の更新を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
落とし穴①:活動実績がなくても更新できると思っている
登録支援機関として「特定技能外国人の支援」を1件も行っていなかった場合でも、更新申請は可能です。しかし、「実績ゼロ=審査が簡単」ではありません。
出入国在留管理庁では、実績がない支援機関に対して支援体制の継続性や、今後の受入見込みを重点的に確認しています。
ある行政書士の実務経験では、「実績がない理由」を形式的にしか書かなかったため、更新が3か月保留となり、その間に更新期間が終了して新規申請に切り替えとなったケースもありました。
落とし穴②:申請期限を過ぎても何とかなると思っている
登録支援機関の更新申請は、有効期限の6か月前の月初〜4か月前の月末が受付期間です。
たとえば、有効期限が10月20日の場合、4月1日〜6月30日が申請期間。7月に入ってしまうと更新申請は一切受理されません。
出入国在留管理庁の内部報告では、「7月以降に駆け込み提出した登録支援機関の約8割が却下」されたという実例もあり、申請タイミングの重要性が浮き彫りです。
申請タイミングを誤ると新規申請として扱われ、登録番号が変わる・履歴が途切れる・手数料が返金されないといった不都合が生じます。
落とし穴③:様式や必要書類が前回と同じだと思っている
登録支援機関の申請様式は、毎年のように細かい変更が行われています。2024年度は「支援責任者の経験年数の具体的記載」が新たに求められ、これを見落とした支援機関が再提出を命じられた例もあります。
また、前回使った様式を使い回した結果、不受理通知が届くというトラブルも実務では珍しくありません。管轄入管の書類チェックは年々厳格化しており、細かい変更も見逃さない姿勢が見られます。
最新版様式のダウンロードとマニュアル確認は必須です。
更新しない場合の対応:廃止届は必須?
活動実績がなく、更新しない場合でも、登録を放置することは絶対に避けましょう。
実際に、廃止届を出さずに登録期限を過ぎた事業者が、次回の新規申請時に「前回の管理不備」を理由に厳しい審査を受けたというケースも報告されています。
廃止届は、登録終了の意思表示として非常に重要です。PDF様式のほか、地域入管によっては郵送・窓口提出が求められるため、事前確認が不可欠です。
まとめ|更新は「何もしなかった人」こそ慎重に
登録支援機関の更新手続きでは、活動していない期間があった場合ほど審査がシビアになります。申請期限の厳守、最新様式の使用、理由書の充実といったポイントを押さえることが求められます。
登録支援機関として「信頼される存在」であるかどうかは、こうした更新時の対応でも問われます。
更新申請が不安な方、または確実に通したい方は、行政書士などの専門家への相談をご検討ください。