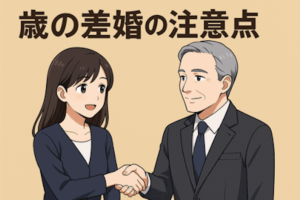【相続人に連絡が取れないとき】どう進める?実務的な対処法と家庭裁判所手続き|比企郡・川越・大宮対応
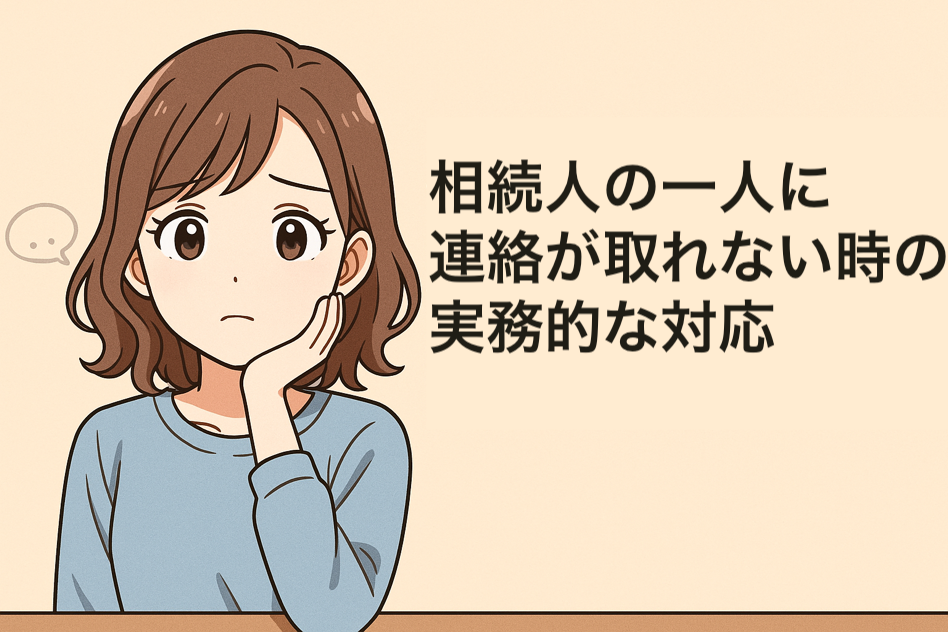
【相続人に連絡が取れない】相続手続きはどう進める?実務対応を行政書士が解説
相続人の一人と連絡が取れない——このようなケースは、実務の現場では決して珍しくありません。今回は、相続手続きの中でも特に厄介な「連絡が取れない相続人がいる場合の対応」について、実際の流れや注意点を詳しく解説します。
相続手続きにおける基本ルール
相続財産を誰がどのように引き継ぐかを決める「遺産分割協議」は、相続人全員で行う必要があります。つまり、たった一人でも協議に参加できない人がいれば、その協議は無効となり、相続手続きを進めることができません。
銀行の預金解約、不動産の名義変更など、どの手続きにも遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印が必要です。
相続人と連絡が取れない原因とは?
連絡が取れない理由はさまざまです。以下のような背景が考えられます:
- 長年音信不通で、現在の居所が不明
- 海外移住していて連絡手段が限られている
- 家族と不仲で、協議への参加を拒んでいる
- 高齢や病気で判断能力が低下している
それぞれの状況に応じて、適切な対応をとる必要があります。
ステップ① 相続人の所在調査を行う
まず最初にやるべきことは、戸籍や住民票などの公的記録から、相続人の現在の住所や生死を調べることです。
具体的な調査方法:
- 戸籍の附票:過去の住所履歴が分かる
- 住民票の除票:転出先が記載されていることがある
- 郵便物の送付:普通郵便・内容証明で連絡
- 親戚や知人への聞き取り:非公式な手段も有効
これらの努力を重ねても連絡が取れない場合は、「所在不明」として法的な手続きに進むことが可能です。
ステップ② 家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立てる
連絡が取れず、居所も不明な相続人がいる場合、家庭裁判所に対して「不在者財産管理人」の選任申立てを行います。
これは、行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加する代理人を裁判所に選任してもらう手続きです。代理人には主に弁護士が選ばれます。
必要書類:
- 申立書(家庭裁判所の所定様式)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 住民票・除票
- 不在者の調査経緯をまとめた資料(記録メモ・送付履歴など)
- 相続関係説明図・財産目録
費用として、予納金(数万円〜十数万円)が必要です。
ステップ③ 不在者財産管理人が協議に参加
選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得たうえで、相続人の代理として遺産分割協議に参加することが可能になります。
協議内容が不在者にとって不利益にならないよう調整され、公正かつ中立な視点で協議が進められます。
ステップ④ 応答しない相続人には「調停・審判」を活用
相続人の居所がわかっているものの、電話や手紙に応答せず、協議に非協力な場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申立てるという選択肢があります。
調停では家庭裁判所の調停委員が仲介役となり、合意形成を促します。調停が不成立の場合には審判に移行し、裁判所が分割内容を決定します。
強制力をもって解決できるため、時間はかかりますが最終的な方法として有効です。
実務上の注意点とアドバイス
- すべての調査・対応履歴を記録しておく(証拠保全)
- 戸籍・住民票の取得範囲は広く丁寧に
- 他の相続人への状況説明と情報共有を欠かさない
- 調停や審判になる場合は弁護士や司法書士とも連携
- 行政書士は戸籍調査・相続関係説明図の作成・不在者手続きの補助が可能
まとめ
- 相続人全員の協議がないと、相続手続きは前に進まない
- 連絡が取れない相続人がいる場合は、まずは徹底した所在調査を
- 所在不明なら家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任申立て
- 応答がないだけなら調停・審判手続きで解決が可能
- 早めの専門家相談が、トラブルの長期化を防ぐカギ
ご相談はエールZEAL国際行政書士事務所へ
東松山・川越・大宮・比企郡(滑川町・嵐山町・小川町・吉見町・鳩山町・ときがわ町・川島町)など、埼玉県内の相続でお困りの方は、当事務所にお任せください。相続人調査から調停対応まで、丁寧にサポートいたします。