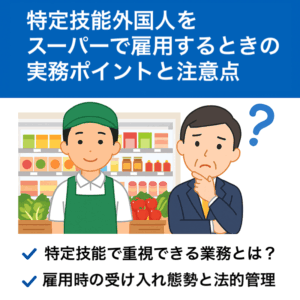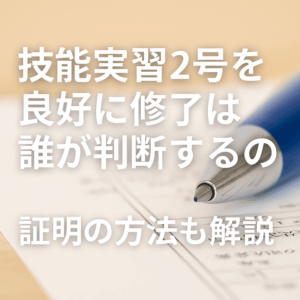【農振除外の壁】農地転用前の最初の関門とは?東松山・熊谷・滑川町対応の行政書士が解説

農振除外の壁 — 農地転用の第一関門
農地転用を考えたとき、最初に立ちはだかるのが「農振除外」という手続きです。農振除外とは、農業振興地域内の農用地区域(青地)を、農業振興計画から外すための手続きです。これを経ない限り、農地転用や開発許可の申請に進むことはできません。農振除外は、農地転用を実現するための“第一関門”であり、計画成功のカギを握る重要なステップです。
農振除外が必要な理由
農業振興地域制度は、農業の安定的振興と農地保全を目的に設けられています。青地と呼ばれる農用地区域は、原則として農業以外の用途に利用できません。そのため、住宅建築や事業用地としての利用を計画していても、農振除外の手続きなしには進めないのです。農振除外は、地域農業やまちづくり計画との整合性が問われる厳格な審査を伴う手続きです。
農振除外審査で重視される4つのポイント
① 代替性の有無
農振除外では、申請地以外に利用可能な土地がないことを証明しなければなりません。周辺に農業振興地域外の土地や宅地がある場合、申請は認められないことが多いです。申請者は、代替地調査を行い、その結果を報告書として提出する必要があります。
「なぜこの土地でなければならないのか」を明確に説明することも求められます。例えば、先祖伝来の土地であること、事業継続上この場所が不可欠であること、物流や立地条件が他の土地では代替できないことなど、客観的かつ具体的な理由が必要です。
② 農業振興に与える影響
農業経営や農業基盤に悪影響を与えると判断された場合、農振除外は認められません。農地の集積を妨げたり、農業用水路や排水路への影響がある場合は、厳しい審査が行われます。以下のポイントがチェックされます。
- 農地のまとまりが維持されているか
- 農業用施設に支障がないか
- 周辺農地との境界が明確で、将来的なトラブルがないか
農業委員会や地元農家との事前協議が欠かせません。異議申出を防ぐため、周辺住民との調整も必要です。
③ 土地改良の有無
土地改良が行われた農地は、改良事業完了から8年以上が経過していないと農振除外が認められません。これは、公共投資により改良された農地の活用を守るためです。申請前には、土地改良区や市町村農政課で事業履歴を確認しましょう。たとえ8年以上経過していても、農業振興上の重要性が高いと判断されれば、除外は認められないこともあります。
④ 地域計画との整合性
農振除外は、市町村の地域計画や都市計画と合致していることが求められます。農地集積推進エリアや市街化調整区域、開発制限区域に該当している場合、申請が認められないことがあります。事前に都市計画課や農政課で確認し、場合によっては計画見直しも検討する必要があります。
実際の事例紹介
成功事例:東松山市内・事業用地での申請
東松山市での事例では、農業用施設に影響を与えない配置計画を策定し、農業委員会・地元農家との綿密な事前調整を行った結果、異議もなくスムーズに農振除外が認められました。
失敗事例:滑川町・住宅建築希望での申請
滑川町では、周辺に宅地が存在するにもかかわらず、農用地区域内で住宅を建てる目的で農振除外を申請した結果、代替性の要件を満たさず却下となりました。事前調査の重要性が改めて浮き彫りになった事例です。
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 申請すれば必ず認められるのですか?
A1. いいえ。要件を満たさない場合や地域計画に反する場合は却下されます。事前調査と事前相談が非常に重要です。
Q2. 地域によって手続きに違いはありますか?
A2. はい。東松山・熊谷・滑川町・嵐山町・吉見町・川越市・坂戸市・鶴ヶ島市など地域ごとに、審査基準や受付時期、必要書類が異なります。
Q3. 相談だけでも受けてもらえますか?
A3. もちろんです。事前相談を通じて、スムーズな手続きをご提案します。
まとめ
農振除外は、十分な準備と的確な対応が求められる手続きです。特に東松山・熊谷・滑川町・嵐山町・吉見町・川越市・坂戸市・鶴ヶ島市では、地域特有の事情を把握した対応が重要です。当事務所では、農振除外手続きに関する豊富な経験を活かし、皆様のご相談をお待ちしております。お気軽にお問い合わせください。