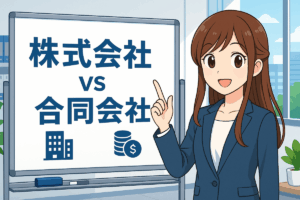【保存版】離婚協議書の作り方と公正証書のポイント|費用・失敗回避・全国Zoom対応

離婚協議書 × 公正証書 × 失敗回避
【保存版】離婚協議書の作り方・公正証書・費用・失敗回避ガイド
(埼玉〈比企郡・滑川町・東松山・川越・さいたま市・熊谷〉/東京・神奈川・千葉・群馬/全国Zoom対応)
はじめてでも迷わないよう、「何を決める・どう書く・いくらかかる・どこで揉める」を、実務で使える粒度まで分解。テンプレ文例・チェックリスト・タイムライン付き。全国Zoomでご相談可能です。
1. 結論:揉めない離婚は「書面+公正証書」が最短
- 離婚協議書=合意の設計図。口約束やLINEのみは証拠力が弱い。
- 公正証書(強制執行認諾文言付き)にすれば、養育費や慰謝料の未払い時に裁判を挟まず差押えを行える可能性があります(※内容により異なる)。
- トラブルの8割は最初の条項設計で回避可能。プロの伴走で「抜け」を潰しましょう。
2. 文書の違い(私文書/公正証書/調停調書)
| 種類 | 強み | 弱み・注意 | 向いている場面 |
|---|---|---|---|
| 私文書(当事者作成) | 手早い/費用低い | 強制力なし。未払い時は別途裁判等が必要 | まず合意を文字化したい/金銭条項が小さい |
| 公正証書(強制執行認諾付) | 金銭債務の未払いに即応できる可能性/証拠力が高い | 手数料・準備あり。条項の精度が要求される | 養育費・慰謝料・分割金など金銭条項がある |
| 調停調書・審判・判決 | 裁判所の関与/強制力あり | 時間と心理的負担が大きい/費用高め | 合意困難/DV等で第三者関与が必須 |
※公正証書の具体的な可否や運用は事案・条項次第です。最終判断は公証役場・弁護士等の指示に従ってください。
3. 必ず決める10項目(抜け漏れゼロの設計)
- 親権・監護:親権者/監護者/住所変更・転校の合意手続
- 養育費:金額・支払日・口座・期間・増減/未払い時対応
- 面会交流:頻度・方法・引渡し場所・長期休暇・代替日
- 財産分与:預貯金・不動産・保険・車・退職金見込
- 慰謝料:有無・金額・分割条件・秘密保持
- 年金分割:按分割合/情報通知書の取得
- 住まい・ローン:住居の帰属/退去・引渡し日/連帯保証の扱い
- 姓・戸籍・住所:氏の取扱い/戸籍の移動/住民票
- 連絡手段・緊急時対応:連絡方法/緊急時の優先順位
- 変更手続き:事情変更時の協議再開条項/紛争解決の方法
4. そのまま使える条項サンプル
養育費(例)
物価その他の事情に著しい変更が生じたときは、甲乙は協議により増減額を定める。
未払い対策(例・公正証書前提)
面会交流(例)
住宅・ローン(例)
5. 進め方:ヒアリング→草案→調整→公証役場→運用
Step1 ヒアリング
現状・子の状況・資産/負債・収入を棚卸し。Zoom可。
Step2 草案作成
抜けと曖昧さを潰す実務条項でドラフトを作成。
Step3 調整
相手方と文言を擦り合わせ。未払い対策・例外処理を詰める。
Step4 公証役場 事前打合せ
必要書類の確認、予約、手数料の概算確認。
Step5 作成当日
本人確認・読み上げ・署名押印。正本・謄本を受領。
Step6 運用
支払管理、連絡ルール、事情変更時の合意書作成フォロー。
※署名手続は原則来所が必要です。事前の原案確認は電話・メール・オンラインで可能です。
6. 必要書類チェックリスト(当事者・公証役場)
当事者側で用意
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 子の情報(氏名・生年月日・学校)
- 金融口座情報(支払・受領口座)
- 資産・負債の一覧(不動産・ローン・保険等)
- 年金分割のための情報通知書(必要な場合)
公証役場で求められやすい資料
- 身分証・住所確認資料
- 条項ごとの裏付け資料(不動産登記事項要約等)
- 委任状(代理人が行く場合)
- 印鑑(公証役場の指示に従う)
※必要書類は事案・役場により異なります。予約時に指示を確認してください。
7. 費用のめやす&モデルケース
| 協議書作成 | ヒアリング/草案/調整サポート。難易度・条項数で変動。 |
|---|---|
| 公証役場 手数料 | 金銭条項の総額に応じて段階的に決定(公証人手数料令)。謄本代・用紙代等の実費あり。 |
| 郵送・追加部数 | 正本/謄本の追加発行・郵送費など実費。 |
養育費 月3万円×10年=360万円、慰謝料100万円 → 金銭条項合計460万円。
公証役場手数料は総額帯により数万円〜十数万円程度になることがあります(詳細は役場見積り)。
協議書作成費は条項数・難易度により変動。無料相談で概算を即時試算します。
※実額は案件・条項・役場運用で変わります。必ず事前見積をご確認ください。
8. タイムライン目安(最短どれくらい?)
- 0週:初回相談(30分/Zoom可)→必要情報の整理
- 1週:草案提示(3〜5営業日目安)→相手方へ提示
- 2〜3週:文言調整→大枠合意→公証役場へ事前相談・予約
- 3〜4週:公正証書作成(当日署名)→運用開始
※合意に時間を要する場合は延びます。逆に合意済みなら2週間前後で完了する例も。
9. よくある失敗10選と回避策
- 金額だけ決めて条項が薄い → 支払日・方法・口座・遅延・事情変更・連絡義務まで条文化。
- 面会交流が曖昧 → 頻度・時間・場所・代替日・オンライン面会を具体化。
- 住宅ローン・連帯保証を放置 → 名義・代償金・解除不可時の代替案まで明記。
- 子のイベント・長期休暇の取り決め無し → 行事優先・分担・長期の追加日を定型化。
- 連絡手段が決まっていない → 連絡方法・既読確認・緊急時の優先連絡先を明記。
- 事情変更時の再協議条項が無い → 物価・進学・転居など変動時の見直し窓口を置く。
- 証拠書類を残していない → 送金明細・面会履歴・連絡記録を保存。
- 第三者の同意が必要な条項を安易に合意 → 金融機関・家主・学校などの手続時期を現実的に。
- 署名後の保管・共有が杜撰 → 正本・謄本の管理、写しの安全な保管を徹底。
- 高葛藤案件で私文書止まり → 金銭条項があるなら公正証書化、必要に応じて法的手続へ。
10. ケース別の作り方
① 住宅ローンが残っている
誰が住む/誰が所有する/連帯保証解除/代償金/売却・住み替えの代替案まで一本道で書く。解除不可のときの次善策を条文化。
② 遠距離・他県居住
面会は隔月や連続日で設定、引渡しは「駅」「公共施設」など明示。オンライン面会を併用し、交通費の負担も決める。
③ 高葛藤・未払いが心配
強制執行認諾付き公正証書を必須に。支払い遅延回数で一括請求/遅延損害金/連絡義務を明確化。
④ 自営業・収入変動が大きい
養育費は相場を踏まえつつ、事情変更時の増減協議条項を厚めに。決算期や賞与・役員報酬の扱いを明記。
⑤ DV・モラハラ・安全配慮が必要
安全確保が最優先。接触・連絡・引渡し方法を厳格化し、第三者立会い・場所の非公開化・弁護士関与を前提に。
11. よくある質問(FAQ)
Q1. 公正証書にしないとダメ?
必須ではありませんが、金銭の未払い対策として強制執行認諾文言付き公正証書が有効です。将来のトラブル予防に強いです。
Q2. 離婚届を先に出してしまいました。
離婚後でも合意書は作れます。公正証書にしておくと未払い時に備えられます。
Q3. 相手が協力してくれません。
交渉文案から始め、難しい場合は調停等を視野に。まずは現状整理と優先順位付けを。
Q4. どれくらいの期間で作れますか?
合意済みなら2週間前後、通常は3〜4週間ほどが目安です(内容・混み具合で変動)。
12. 相談方法(関東・全国Zoom対応)
初回相談:30分(Zoom/電話/対面)—現状整理・方針決定・概算費用の即時試算まで。平日夜・土日も対応可。
対象地域:埼玉(比企郡・滑川町・東松山・川越・さいたま市・熊谷)/東京/神奈川/千葉/群馬。遠方の方も全国Zoomで対応します。