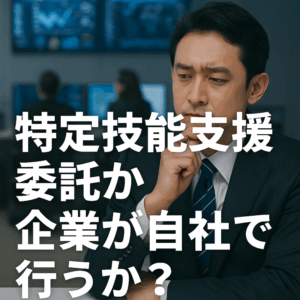【農地転用】申請すれば通ると思ってない?却下される5つの理由と成功のポイント
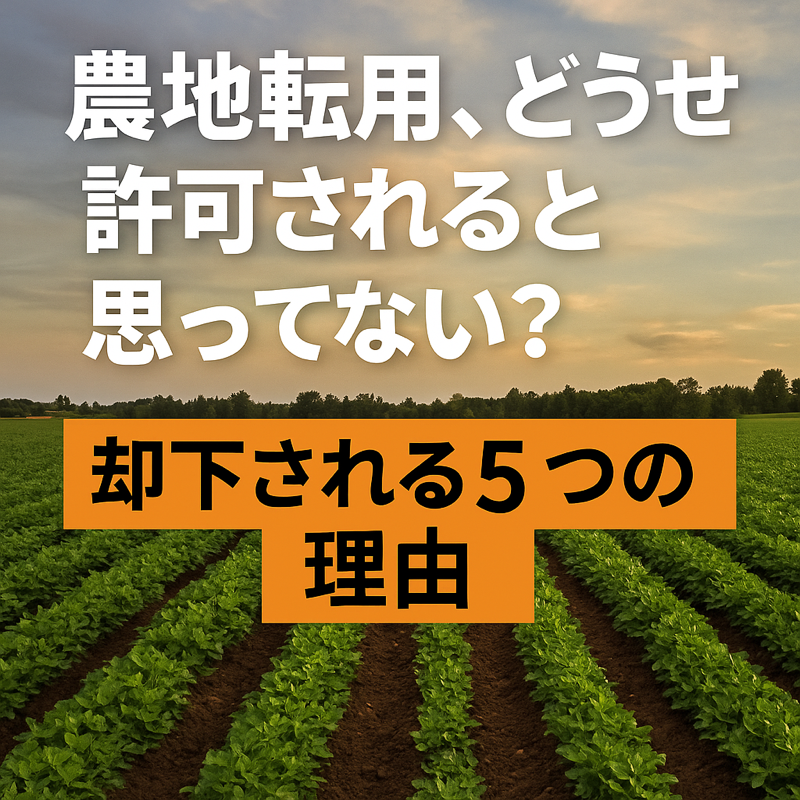
農地転用、どうせ許可されると思ってない?【却下される5つの理由】
「農地転用なんて、申請すればどうせ許可されるでしょ?」
そんな風に考えていませんか?
実は、農地転用は非常に厳格な審査を経て許可されるものであり、単に申請すれば通るものではありません。
準備不足や法律への理解不足から、あっさり却下されてしまうケースも珍しくありません。
この記事では、農地転用の手続きに不慣れな方でも理解できるよう、行政書士の視点から「却下される5つの理由」と、成功のためのポイントを詳しく解説していきます。
1.転用目的が不明確・必要書類が不足している
農地転用は、ただ「農地を別の用途に使いたい」と言うだけでは許可されません。
行政は、その計画が実現可能で、適切に運用されるかどうかを厳しくチェックします。
たとえば「資材置場にしたい」と申請する場合、
・資材の種類や管理方法
・整備計画、造成内容
・排水計画や交通アクセス
まで具体的に説明した書面が必要になります。
これに加え、土地の現況写真や詳細な位置図、登記事項証明書、周辺見取り図など、求められる書類は多岐にわたります。
これらが一つでも欠けていたり、内容が不備だと、審査は即ストップ。
最悪の場合、申請を受理してもらえないことすらあります。
事前の書類チェックと、農地転用に詳しい専門家への相談が不可欠です。
2.都市計画法との抵触による却下
農地法だけで話を進めてしまうのは危険です。
なぜなら、農地の所在地が「市街化調整区域」にある場合、都市計画法による厳しい規制があるからです。
市街化調整区域では、原則として開発行為が禁止されています。
そのため、農地転用の申請以前に「開発許可が必要」であったり、「そもそも用途変更が不可能」な場合も。
この確認を怠って農業委員会に申請しても、都市計画法に違反するために却下となるのがオチです。
管轄の都市計画課や建築指導課への事前相談は、絶対に外せないステップです。
3.申請者の適格性が問われるケース
農地転用申請は、「転用後にその土地を使用・管理する予定の者」しか提出できません。
名義貸しや、実態のないペーパーカンパニーが申請しても、まず認められません。
さらに、
・申請者が事業実績のない個人だった
・資金力が不十分で事業継続性が疑われた
・本当にその用途で使用するのか不明だった
といった理由で、実現性がないと判断され却下されることもあります。
金融機関からの資金調達状況や、同種事業の実績、事業計画書の整合性など、審査官が納得できる材料を整えておくことが重要です。
4.周辺環境・近隣住民との調整不足
農地転用後の土地利用が、周辺環境や住民に与える影響も、審査で重要視されます。
たとえば、
- 大型資材置場が近隣の住環境を悪化させる
- 太陽光発電施設が景観や農業活動に悪影響を与える
- 通行道路が狭く、車両通行が困難になる
といった理由で、近隣住民から反対意見が出れば審査は難航します。
事前の説明会や、同意書の取得を求められることもありますので、地域との調和を意識した計画作りが求められます。
5.農地法の趣旨に反した転用理由
農地法の基本理念は「農地を守ること」です。
このため、農地の転用が農地保全の理念に反していると判断されれば、許可はおりません。
以下のようなケースでは、趣旨違反で却下されることがあります:
- 農業振興地域内の農地を住宅地に転用
- 農地が集積しているエリアで転用申請
- 農業用水や農道への影響が大きい事業
特に、農業振興地域整備計画に指定されている農地は要注意。
農業委員会だけでなく、県の農業振興課とも連携を取ったうえで慎重に進めるべきです。
成功するための事前準備のポイント
農地転用申請を成功させるには、次の5つが重要です:
- 法令チェック:農地法だけでなく都市計画法や建築基準法も確認
- 用途と計画の具体化:転用目的を明確にし、事業計画書に落とし込む
- 申請者の信用・実績確認:資金力・過去実績を整えた上で臨む
- 近隣住民との事前協議:誤解や反対を避けるため、事前説明の徹底
- 専門家への相談:行政書士など専門家のチェックを受ける
まとめ|農地転用は「誰にでもできる手続き」ではない
農地転用の手続きは、単に申請書を出せば通るものではありません。
地域によって審査基準や手続きの流れが異なり、慎重な事前調査が不可欠です。
特に埼玉県(東松山・熊谷・滑川町・嵐山町・川越・大宮)のような地域では、地域特有の農業振興計画や土地利用制限があるため、地元に精通した行政書士に相談することが成功のカギとなります。
当事務所では、農地転用に関わる各種相談から、事前協議、申請書作成、提出代行までワンストップで対応可能です。
まずはお気軽にご相談ください。